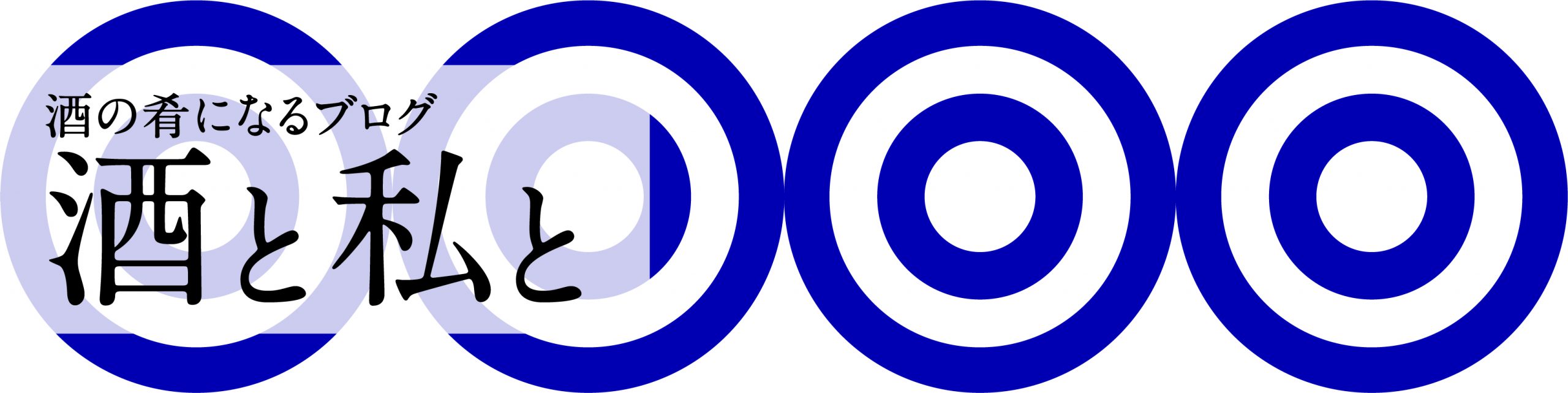好むと好まざるとに関わらず、そこに良い思い出があろうとなかろうと、故郷とは人にとって特別な場所である。自分が生まれ、育ち、後にした町は、時を経て姿を変えたとしても、在りし日の記憶をありありと呼び起こす。ここで育ったのだという決定的な事実を覆すことは、誰にもできないのだ。
私にとっては、埼玉県の最南端に位置する所沢市が故郷にあたる。都心から電車で1時間足らず、西武鉄道の本社があり、所沢駅には西武池袋線と西武新宿線が乗り入れ、埼玉西武ライオンズの本拠地であるベルーナドームがあり、西武園ゆうえんちをはじめとする西武グループの施設が立ち並ぶ、いわゆる西武王国と呼ばれる町である。その割に、成人した地元民の多くは西武線に乗って都心の企業へ務めに行くという、東京のベッドタウンとしての側面も持ち合わせている。
今でこそ東京都内に居を構えている私だが、実家は変わらず所沢にあり、また時おり地元の友人と会うこともあるため、年に数回は里帰りを行っている。ここに住んでいる人ならば気付きにくいと思うが、私のような人間がたまにこの場所を訪れると、些細な町の変化にも敏感に反応してしまうし、大きな変化には戸惑いすら感じてしまうものだ。所沢駅が大規模なショッピングモールを併設したリニューアル工事を行った直後などは、あまりの変化に右も左もわからなくなり、若干迷子になってしまったことすらある。私が学生時代にアルバイトをしていた駅ビルの居酒屋はなくなり、駅のホームで燻し銀の光を放っていた立ち食いそば屋はすっかりおしゃれでスタイリッシュな装いをまとった。西武鉄道の象徴であったはずの黄色い電車はすっかり見なくなり、シルバーにブルーやレインボーのラインが入った車両が幅を効かせるようになった。昔は良かった、などと自分が生まれ育った時代の正当性を主張するつもりはない。むしろ時代の変遷やニーズの変化に対応してアップデートを繰り返してきた、この町の健康で健全な営みを評価するべきなのだろう。変化し続けなければ、老いていく。町にも人にも同じことが言えるのかもしれない。
ある休日の午後、ちょっとした野暮用を片付けるため、私は久しぶりに所沢の実家を訪れていた。早々に用を済ませ、お茶を飲みながらだらだらしていると、次第に日が傾きはじめた。晩ご飯食べていけば?という母の誘いをやんわりと断り、また来るよ、と実家を出る。この時の私の顔には、何か良からぬことを企んでいるような、薄気味悪い笑みが浮かんでいたかもしれない。お茶を飲みながらだらだらしている最中、とある計画を思い浮かべていたのだ。今日は夕方から自由な時間が確保できる、これは呑みに行けるな、そう言えば所沢でひとり呑みをしたことがない、行くならあの店しかないな…。実に酒呑みの私らしい、稚拙で低知能な計画ではないか。まるで遊園地へ向かう子供のように、ウキウキとしながら所沢駅西口に広がる商店街「プロぺ通り」をめざした。

所沢で呑むならここは外せないだろう、という名店がある。それが「百味」だ。歴史を紐解いて驚いたのだが、百味は実に50年以上にもわたり、この地で愛され続けてきたという。コロナ禍の煽りを受けた2020年に閉店すると聞かされた時、それはそれは残念な思いを抱いたのだが、同じ年に新オーナーのもとで見事な復活を遂げた。昼呑みも楽しめる11時から23時までのロング営業、席数200以上の大箱、刺身・串焼き・煮物・揚げ物・定食まで昼夜問わず多彩な食が楽しめて、しかもリーズナブル。ちょっと非の打ち所がない大衆酒場なのだ。
私は幼い頃からこの店の存在は認知していたし、かつてバイト仲間と数回訪れてはいるが、ひとりで乗り込んだのは今回がはじめて。思えば私の父も、近場に住む親戚たちも、何気ない会話からそれぞれが漏れなくここを訪れていたことを知っている。付き合いが長いと言えば語弊があるが、何となく縁があるというか、必ず訪れなければという思いを一方的に抱いていた店なのだ。
地下への階段を降り暖簾をかき分けると、さすがは名店、さすがは休日の夕方、これぞ酒場といった盛り上がりを見せている。テーブル席、小上がり席、そしてカウンター席が、人と酒で埋め尽くされている。店員にひとりであることを告げると、奥まったカウンター席へ案内された。盛り上がる酒場の、比較的静かなカウンター席。ひとり客にとってはありがたいポジションだ。希望にかなう席に座れたというだけで、酒呑みのテンションは格段に上がっていく。酒と酔いに向き合う万全の体勢が整ったとでも言うかのように。


もうビールはこれだけでいいとすら思える赤星で喉を潤し、冷やしトマトのマヨネーズで口内の塩分濃度を高めていく。なんの変哲もないメニュー、だが故郷の名店の喧騒に包まれながら味わうそれは、どこか意味深いもののように感じるのだから不思議なものだ。

赤星を中心にひと通り味わったので、次のフェーズへと歩を進めていく。選んだのは、真澄とサバの塩焼きである。オーダーが通っているのか若干不安を覚えるころにやってきたサバの塩焼きは脂の乗りが豊かで、すっきりとした真澄との相性がとてもよろしい。こんなことはあまりやらないのだけれど、思わず目を閉じて、そのマリアージュをじっくりと楽しんだ。焼き魚で呑む酒もいいもんだなと、改めて感動を覚えるほどであった。

ぼんやりと店内を見渡すと、相も変わらず大勢の酔客が楽しげな宴を繰り広げている。7割ほどのおじさんと、3割ほどのおばさん、といったところだろうか。おじさんやおばさんなどと呼んでしまったが、実際には私と大きく歳が離れているわけでもないだろう。そして彼らのうちの少なくない割合が、幼少期に私が見た所沢の風景と、同じものを見てきただろうと推測できる。話しかけられたなら、地元の昔話に花を咲かせることができるかもしれない。共通の友人がいることを喜ぶかもしれない。いや、実は歳をとっただけの古いクラスメイトが混じっているかもしれない。そんなことを際限なく考えながら、ちびりちびりとお酒を味わい続ける。いつもより強く酔いを感じたのは、故郷にいることの安堵感と、記憶のなかから甦った古い町並みの残像によるのかもしれない。
地上への階段を気だるく登り、駅へ向かってとぼとぼと歩いていく。これから西武線に乗り、東京の自宅へ戻らなくてはならない。そしてまた、普段通りの現実に向き合わなければならないのだ。親に守られながらなんの悩みもなくのうのうと生きていた時代に戻りてぇなあ、などど思う。一方で、短くない自分の人生で積み上げてきたものを全部使って、まだまだやりたいことがあるんだよな、とも思う。
秋に差し掛かった所沢の夜、見上げるとそこには優しい光が滲んでいた。