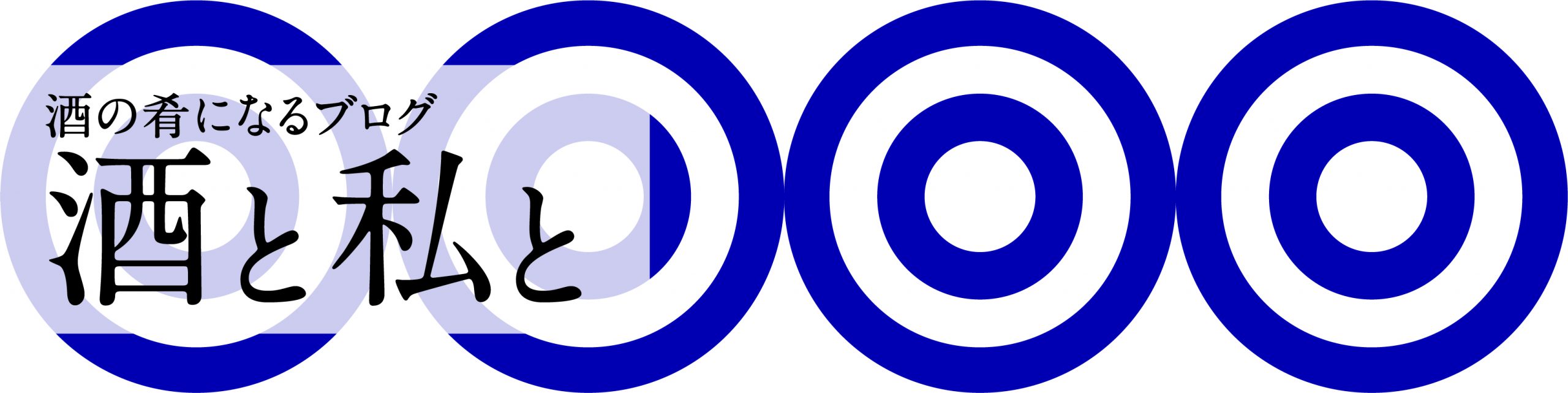親愛なる酒呑みのみなさんならば、思い出に残っている酒場について聞かれたとき、思い浮かべる店がいくつかあるだろう。学生時代によく足を運んでいた店、恋人と定期的に通っていた店、地元の懐かしい店、足繁く通っていたものの惜しくも閉店してしまった店、などなど。私にもそんなお店がいつくかあるのだが、今回紹介するお店はちょっと特殊で、でも私の若かりし頃の思い出がつまった場所。かつて有楽町のガード下にあった、まるで日常とはかけ離れたような存在感を放っていた「食安商店」である。
有楽町ガード下で異彩を放っていた「食安商店」

食安商店を酒場や居酒屋、立ち飲み屋と呼んでもよいのか、若干悩むところではある。正確には店というか「自動販売機コーナー」だったのだ。小さな店内に並ぶ自販機で缶ビールや缶チューハイなどを買い、時間によっては自販機の隙間で店員さんがスナックや乾き物を売っているので気分でそれを買い、同じく店内に設置された立ち飲み用のテーブルで酒とつまみを楽しむという独自のスタイル。テーブルの端には灰皿が設置されていたので酒呑みの愛煙家にはたまらない環境だったのではないだろうか。
この自由で気軽な空気感が広く受け入れられていたのだろう、仕事帰りのサラリーマンはもちろん、日中ですらスーツ姿で缶ビールを煽るツワモノもいたように記憶している。それどころか買い物帰りの主婦風な女性や子連れの若いママ、スーツ姿の外国人も目撃したりと、非常に幅広い客層に受け入れられていたようだ。
食安商店の開業について正確なデータは見つけられなかったが、JR有楽町駅周辺は戦後の闇市から発展したエリアと言われており、ガード下には当時から多くの飲食店が軒を連ねていたことから、食安商店もその流れのなかで生まれた店のひとつなのではないかと推測できる。いかにも長年の風雪に耐えてきたであろう店内の風情は味わい深く、晩年には「昭和レトロ」を追い求める若い世代の客も増えていたという。
そんな酒呑みのオアシスであった食安商店は2020年4月に惜しまれつつ閉店。建物の老朽化や近隣の再開発などが閉店の理由と考えられている。
かつての私のネガティブな感情を脱ぎ捨てることができた場所
そんな食安商店と私との出会いは、私が30歳前後のころだったと記憶している。当時の私は銀座にある会社に務めており、なかなかにブラックな職場環境のもと昼も夜もなく働きずくめていた。その日も気づいたら終電間際の時間になり、そろそろ帰ろうかと思っていたところに、同じ部署で働く先輩が私に声をかけてきた。「ちょっと一杯呑んで帰ろう」。そろそろ帰りたいんですけど、明日も早いんですけど、というか最近あんまり寝てないんですけど、という私の反抗も虚しく、半ば無理矢理に連れて行かれたのが食安商店なのであった。
最初こそ気乗りしていなかったものの、この場所の気軽さとなんとも言えない風情に、私の心は少しときめいてしまったのだ。お酒は自販機の価格だから小銭で呑める、それでいてコンビニで買って道端で呑むような罪悪感も一切ない、なにより終電間際なのに多くの酔客で賑わっていることの仲間意識というか酒呑み同士に守られているような感覚。疲れと睡眠不足で弱りきった身体に染み渡った缶チューハイの名残も相まって、ここいいなぁと思わされたのだ。
それ以来、私はことあるごとに食安商店に足を向けるようになった。仕事のあとひとりで、仕事終わりに同僚たちと、また銀座や有楽町周辺での呑み会あとひとりでシメの一杯を楽しんだりもした。昭和の風情を残す店内、でも振り返れば有楽町のビル群が現実として眼の前にそびえ立っている。そんな非日常感の中で呑むお酒は、間違いなく私ががむしゃらにむちゃくちゃに働いていた時代の癒やしのひとつであったし、当時私が抱えていた虚しさや不安や寂しさをこの店に脱ぎ捨てることで、どうにか正気を保っていたとも言えるのだった。
再開発の名のもとに、魅力を失っていく東京の街
 やがて私が銀座の会社を去り、食安商店の存在も私の中で風化しつつあったころ、突然「食安商店閉店」のネットニュースに触れることになる。しばらく行っていなかったこともあり大きな落胆はなかったのだが、それでもやはりあの頃のことを思い出しては残念な気持ちになったことを覚えている。
やがて私が銀座の会社を去り、食安商店の存在も私の中で風化しつつあったころ、突然「食安商店閉店」のネットニュースに触れることになる。しばらく行っていなかったこともあり大きな落胆はなかったのだが、それでもやはりあの頃のことを思い出しては残念な気持ちになったことを覚えている。
再開発の名のもとに、食安商店のような昭和の風情を残す店や風景は次々と姿を消していく。その後に建てられるのは、おしゃれできらきらして、歴史からも地域性からも分断された大手資本による店舗とオフィスたちだ。東京の街それぞれが持つ独自の魅力が消えてなくなり、今やどの街へ行っても同じような店舗やビルばかりが並ぶようになってしまった。これも時代の流れだと言われればそれまでだけど、魅力のない街を作ることを再開発と呼ぶのであれば、私たちはいったいどこをめざしていると言うのだろう。