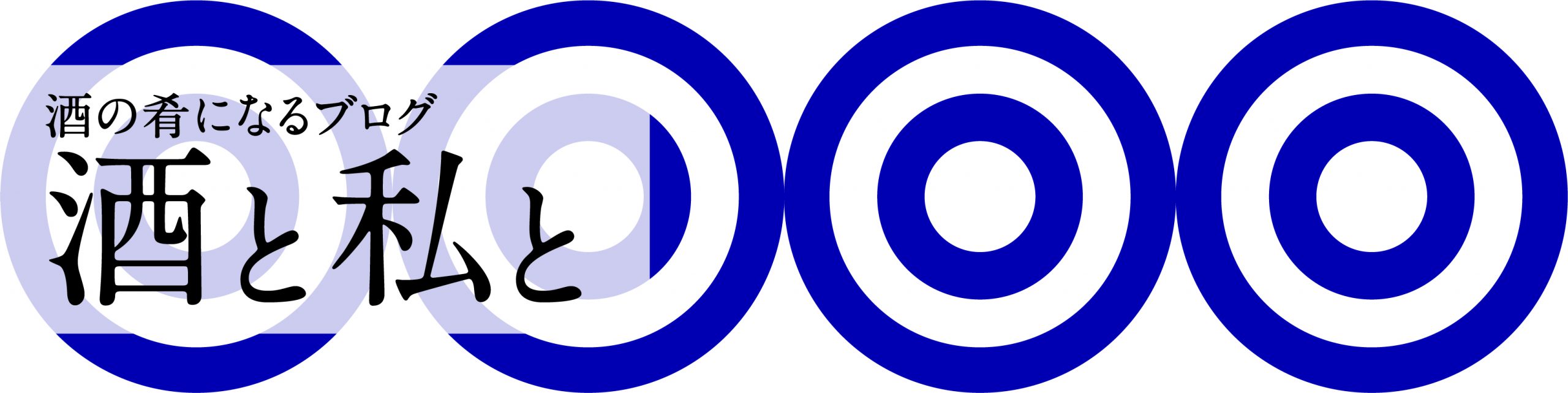趣味は何かと問われれば「酒を楽しむこと」「酒場をめぐること」と答えてきた。それは今でも変わらない私の正直な気持ちであり、これからも変わることなどないだろうと感じる。ところが近ごろ、これらふたつの趣味に加え、3つめの趣味が誕生しようとしている。こんなことがあって良いのだろうか。このどうしようもない、ろくでもない酒呑みであるこの私が、恐れ多くもこんなことを趣味にしようとしているなんて。言葉に表すこともはばかられる、その趣味の名は「キャンプ」なのである。
酒と焚火の愉悦を知ってしまった。
恥ずかしげもなく「キャンプ」だなどとのたまったが、しかししかし、そこはさすがにこの酒呑みのやることである。自然の息吹を感じながら、おしゃれなテントとキャンプグッズに囲まれてローストビーフをこしらえたり、大皿に小さく盛られたパスタをおちょぼ口で食べようというのではない(大いなる偏見失礼)。
「キャンプ」と大枠に語ってみたが、実際のところ、私の目的はキャンプ以上に「焚火」なのである。焚火を眺めながら酒を呑む。焚火をいじりながら酒を呑む。いい歳になって、この行為の愉悦を知ってしまったのだ。史上最強のおつまみは焚火であり、これからの人生を酒と焚火とともに歩んでいきたいと思わせるほど、焚火の魅力は強く奥深いと感じている。
準備万端に整えなければ焚火ははじまらない。
焚火の魅力に覚醒した先日のキャンプは、以下のようなポジションで行われた。焚火台正面の椅子に私が腰をおろし、右側に酒や氷をたんまりと詰め込んだクーラーボックスを配置。そして左側にローテーブルを置き、その上に調理用ガスバーナーとスーパーで買ってきたさまざまなおつまみ、そしてお気に入りのサーモスマグで準備万端である。
夜の帳が下りるのを見計らい、おもむろに焚火台に点火。はじめは小さな頼りない火を、酒を呑み、つまみを味わいながら、時間と手間をかけてゆっくりと育てていく。
1本目の350mlビールをあっという間に空け、右手のクーラーボックスから2本目を取り出して開栓。これも呑み干すのに時間はかからない。サーモスマグに氷を放り込み、いいちこを気持ち多めの目分量、最後に炭酸水を目一杯追加して、いつものお手製酎ハイを呑みはじめるころには、気持ちはかなりの高揚感に包まれていた。
刹那の連続、それが焚火の魅力。

思えば、幼い頃から火を見るのが好きだったなあ、と思う。母親が庭で焚火をはじめようものなら、漫画を読んでいようがゲームをやっていようが昼寝をしていようが、すべてを放り出して庭へ出ていったし、林間学校での女子とのフォークダンスは苦手だったけど、燃え盛るキャンプファイヤーはずっと見ていたいと思っていたものだ。
火は、海の波と同じで、時々刻々とその形を変えていく。同じ姿は二度となく、唯一の一瞬が、ただ延々と続いていく。そんな刹那の魅力に強く惹かれるのかもしれない。
大きな薪の、無に帰するを見る。
この日の最後に、片手では掴みきれないほど大きな広葉樹の薪がひとつ残った。普通であれば斧などで割り、もう少し手頃な大きさにして使うべきなのだけれど、お酒の勢いも手伝ってそのまま火にくべてみた。大きな薪が炎に包まれながら、色を変え、形を変え、徐々にその存在を小さくしていく。そして熾火(おきび)として煌々と輝いたあと、その薪は真っ白な灰となり無に帰する。まるで、さざれ石の巌となりて苔のむすまで、を体現するかのような長い時間、私は薪の燃え尽きるさまを飽きることなく見届けた。こんなにも思慮深く、こんなにも豊かな時間がほかにあるだろうか。
酒と焚火、ぜひお試しあれ。
長々と語ってきたが、これは私がそれほどまでに焚火の魅力に取りつかれたことの証左である。焚火とともに呑む酒の、いかに美味いことか。この魅力を、親愛なる酒呑みのみなさんにもぜひ感じてもらいたいと思う。キャンプという体裁をとる必要はない。どこかそれが許される場所で試してもらえたなら、きっとわかってもらえるんじゃないかなと思う。
いつか、毎晩焚火ができる土地に移住しようかな、リビングに暖炉を設置するのもいいね、などなど、無謀な夢や妄想がどんどん広がっていく。