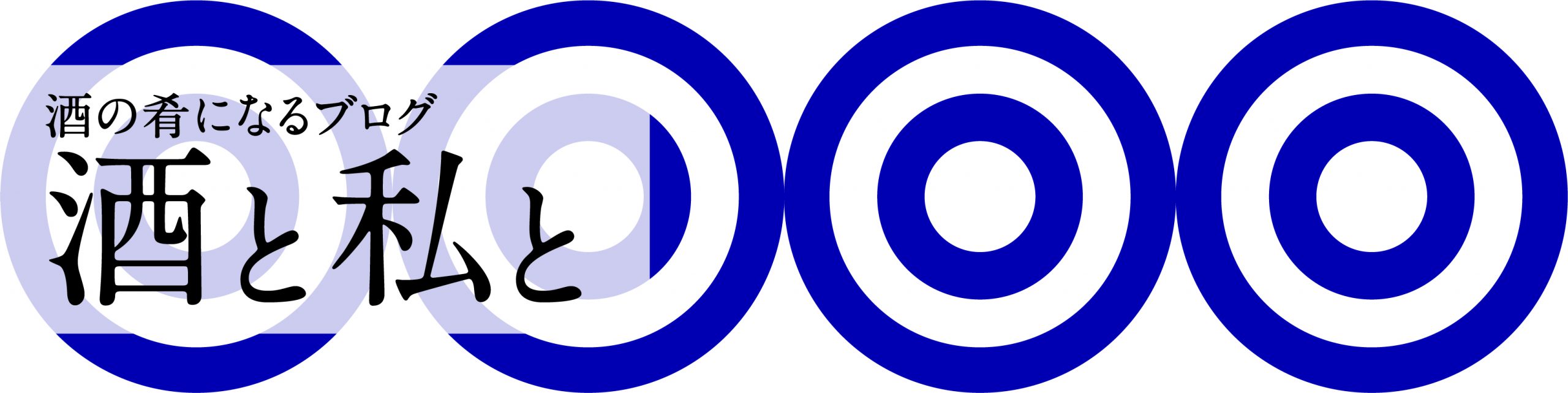ひとりふらりと酒場を訪れては酔っ払い、あるいは自宅で晩酌や寝酒をキメた挙句、SNSで意味のわからないウワゴトを呟いている。それが私ということで間違いはないのだが、こんな私にも実はライターという本業がある。この仕事をけっこう長く続けているため、職業病というか、カタギの人々が特に気にしないような言葉の使い方などに対して、けっこう敏感になっているフシがある。その言葉の使い方、間違ってない?そういう意味じゃないのでは?そんな違和感のようなものを感じることがけっこうあり、そのなかでも代表的なものが「秘伝」なのである。
「秘伝」という二文字の持つ響きには、人を惹きつける魅力のようなものがあるのだろう。メディアやネットで、そして飲食店でも見かけることがとても多いと感じる。近年、この「秘伝」という言葉があまりに軽んじられているのではないか、本来の意味から逸脱して、便利でキャッチーな言葉として消費されすぎているのではないかと思っている。今回の記事では、私が一方的に感じている「秘伝」への違和感と、その対処法のようなものを紹介したい。「新規オープンの店が秘伝のタレを使っている?」そんな違和感を感じたことのある方であれば、きっと共感していただけると思うのだが、どうだろうか。
「秘伝」という言葉の本来の重み

本来、「秘伝」とは軽々しく口にするものではなかった。料理に限らず、武道や芸能などの世界において、特定の師から特定の弟子へと、口伝でのみ伝えられる高度な技術や知識のことを秘伝と呼んでいた。書物に書き残さないのは、技を盗まれることを防ぐため。そして、その技術を守り続けることは、家業や流派の誇りでもあったという。
たとえば老舗のうなぎ屋が100年以上使い続けている「継ぎ足しのタレ」。毎日の営業で減った分だけ同じ配合の新しいタレを足し、長い時間をかけて旨味が幾重にも蓄積されていく。これこそが真の意味での秘伝。歴史そのものが旨味成分となり、新参者には到底真似できない奥深さが宿っているのだ。
ところが現代では、この「秘伝」がチェーン居酒屋のPOPやコンビニスナック菓子の袋にすら印刷されている。袋の裏を見れば「しょうゆ、砂糖、みりん、その他」と素っ気なく記載されているのに、表では堂々と「秘伝の味」を謳う。これこそが、私が感じている違和感そのものなのだ。
「秘伝」が軽くなった理由

おそらく、広告コピーとして「秘伝」はとても便利な言葉なのだろう。「自家製」よりも響きがよく、「オリジナル」よりも物語性がある。さらに具体的な根拠を示さなくても「秘伝」と謳うだけで何やら特別感が漂っているように感じられるんだからたちが悪い。テレビのグルメ番組では、新規オープンの店であるにも関わらず、その店独自の味付けに対していとも簡単に「秘伝のタレ」などと紹介する。動画サイトでは、投稿主が考えた味付けに対して自ら「秘伝の味」などとのたまう。
飲食店や食品販売業者の立場で考えると、キャッチーな言葉を利用して売上をめざす姿勢は当然である。お客さんが足を止めてくれなければ商売が成り立たないという実情も痛いほど理解できる。ただ消費者側、特に私のような皮肉屋にとっては、この言葉に慣れすぎた結果、むしろ「秘伝」と書いてある方が怪しく感じる、という皮肉な現象が起きているのも事実なのではないかと考える。
酒場文化における「秘伝」

酒場を巡っていると「秘伝のタレ」や「秘伝の味付け」に出会う機会は多い。特に焼鳥、もつ焼き、唐揚げ、このあたりは秘伝率が高い。そして面白いことに、そういう店の中には、本当にしっかり美味しいところと、「まあ普通かな…」で終わるところが混在している。
私の経験則では、本当に味の良い店ほど「秘伝」という言葉を使わない。代わりに「創業昭和○年」とか「継ぎ足し○十年」といった具体的な数字や歴史を提示してくる。その方が説得力があるし、なにより「本物感」が感じられて、じゃあ味わってみようかと思えるのだ。
逆に、メニューや看板でやたら「秘伝」を連呼する店は、味よりもイメージで勝負している場合が多い。もちろんそれが悪いわけではないが、酒場好きとしては、どうしても身構えてしまうのだ。「ああ、この秘伝には気をつけよう」と。
秘伝を見抜く5つの質問
「秘伝」という言葉に出会ったとき、すぐに信じて食べてみるのも面白いが、せっかくならちょっと探偵気分で確かめてみるのも良いだろう。
以下の5つの質問を心の中で、またはお店の人にさりげなく投げてみると、その秘伝が本物なのか、秘伝風なのかが見えてくると思う。
いつから使っているタレ(または味付け)?
→年数や代が具体的に出てくれば本物。「去年からです」だと秘伝風。
誰が最初に考案した?
→創業者や先代の名前が出ると物語性が強い。逆に「スタッフで話し合って決めました」だと、まだ歴史は浅い。
どこで作っている?
→店内仕込みなら伝承度が高め。業務用メーカーの工場製だと「秘伝監修」かもしれない。
何代目?
→「三代目です」など代数が出れば、家業や継承の匂いが濃厚。ゼロ代目(開業オーナー本人)の場合は、まだこれから育つ秘伝。
毎日味が変わる?
→「気温や湿度で変わるので微調整します」と答える店は、本当に人の手で守られている証拠。逆に「全く同じです!」は、それはそれで安定感のある工業製品由来の秘伝風。
「秘伝」とうまく付き合う

結局のところ、本物の秘伝であっても、秘伝風のものであっても、食べて美味しければそれでいい。ただ看板に「秘伝」とあれば、少しだけ疑いの目を持ちつつ、舌で確かめにいくのもまた一興だ。
もし本物の秘伝だったら、それはもう小さな宝物を見つけたような喜びがある。そして秘伝風であれば、それはそれで「話のネタ」という酒場の会話の調味料がひとつ増えるだけだ。
ライターのようなアコギな商売をしていると、また酒場巡りを続けていると、こうした言葉の使われ方にも敏感になっていく。「秘伝」という二文字に込められた真実と虚飾、そのあいだを楽しむことも、酒場の醍醐味なのではないかと思っている。