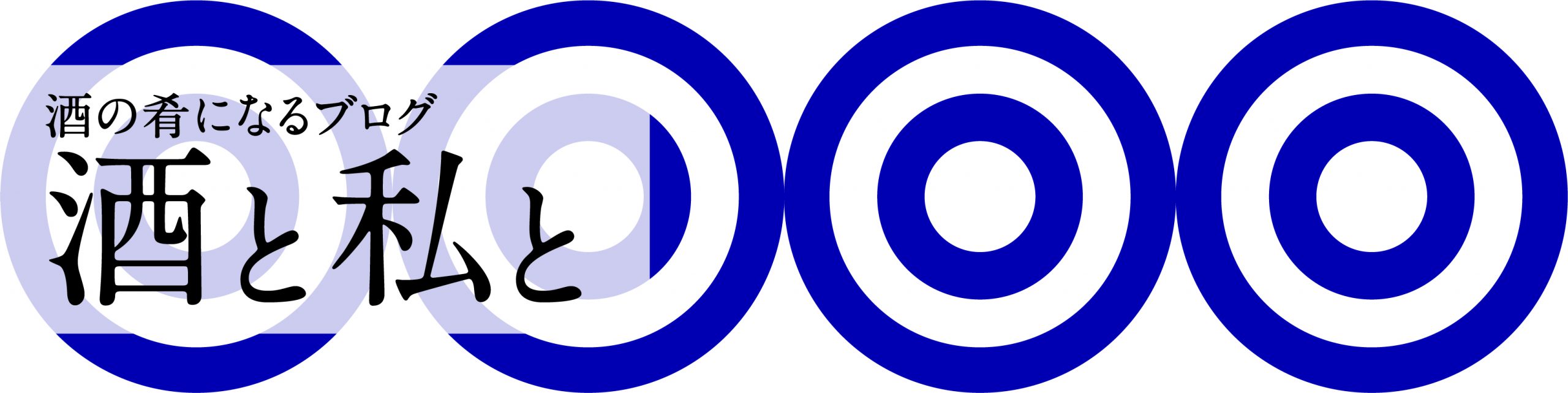以前の記事で、はじめて訪れる酒場を楽しむためのマイルールを紹介した。「共感できる」「自分とまったく違う」などさまざまな反応が得られて嬉しい限り。そこで今回は、何度か足を運んだことのある、なじみの店をより楽しむために私が心がけているマイルールを8つご紹介しようと思う。
とはいえ、私自身はさまざまな街のさまざまな酒場を転々と歩き回りたいタイプなので、顔なじみの店や常連となっている酒場は皆無である。「こんちは」「お、今日は早いね」みたいな店主とのやりとりに憧れがないわけでもないのだが、酒場を訪れる機会そのものが多くない私の立場上、その希少な機会をできるだけ新しい酒場体験に費やしたいと思っているのだ。
もちろん、多くの酒場を巡るなかで「この店こそ」と思える店には、応援の意味も込めてできる限り再訪したいと考えている。ここまでの文章で大いなる矛盾が生じていることは承知のうえで、応援したい店、何度でも通いたい店での時間を濃密なものとするために、いつの間にか自分のなかでルールというか習慣というか、工夫のようなものが存在していることに気づいたのだ。ただなんとなく呑むだけでなく、限られた贅沢な時間を余すことなく味わうための参考となれば幸いである。(100倍、はあくまでも当社比です)
- なじみの酒場を楽しむためのマイルール①「呑みながらやることをなんとなく決めておく」
- なじみの酒場を楽しむためのマイルール②「できれば空いている時間に入る」
- なじみの酒場を楽しむためのマイルール③「季節のメニューはおさえておく」
- なじみの酒場を楽しむためのマイルール④「はじめてのメニューにチャレンジする」
- なじみの酒場を楽しむためのマイルール⑤「おつまみは「ちょっと足りない」くらいにとどめる」
- なじみの酒場を楽しむためのマイルール⑥「日本酒は2合まで」
- なじみの酒場を楽しむためのマイルール⑦「店内の音と風景を楽しむ」
- なじみの酒場を楽しむためのマイルール⑧「締めたくなったら蕎麦にする」
- もっと豊かな酒場時間のために
なじみの酒場を楽しむためのマイルール①「呑みながらやることをなんとなく決めておく」

ひとり呑みは、自由であるがゆえに油断するとただの「時間潰し」になってしまうという懸念もつきまとう。そこで私は「今日はこれをやろう」というテーマをぼんやりと決めてから暖簾をくぐることにしている。
私が酒場でやっていることは以前の記事に詳しいが、たとえば、ある日は仕事のアイデアをスマホに書き出す。ある日は文庫本を一冊持ち込み、お酒を味わいながら気ままにページをめくる。何も考えずにカウンター越しの厨房を眺め、店主やスタッフの所作を眺めることだって立派なテーマとなりうるだろう。
ただ酔うだけで終わらせない。そこに小さな芯を通すだけで、ひとり呑みは「自分と向き合う時間」へと昇華させることができるのだ。
なじみの酒場を楽しむためのマイルール②「できれば空いている時間に入る」
人気の酒場は、夜7時を過ぎれば常連と一見が入り乱れ、賑やかに盛り上がる。もちろん、それはそれで悪いことではないのだが、ひとり呑みには少しばかり喧騒が過ぎるというもの。だから私は、都合の許す限り早い時間に足を運ぶ。開店直後の時間が特におすすめだ。
午後5時、まだ外は明るいのに暖簾を押すあの背徳感。カウンターには数人の常連がすでに宴をはじめており、テレビからは夕方のニュースが流れている。店主は常連と軽口を叩く余裕もあり、注文のやりとりも落ち着いている。混んでからでは見逃しがちな、ちょっとした気遣いや会話が、早い時間帯にはきちんと受け止めることができる。
酒場は、同じ空間でも時間が異なればその表情はまるで違ったものになる。ひとり呑みを楽しむなら、その静けさを独り占めするのが贅沢というものだろう。
なじみの酒場を楽しむためのマイルール③「季節のメニューはおさえておく」
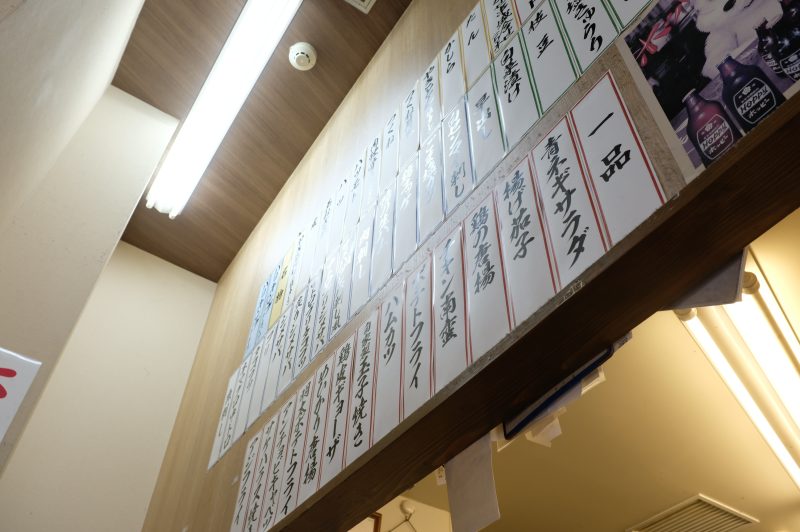
良い酒場であればあるほど旬の食材を巧みに使い、その時期ならではのおつまみを用意してくれている。なじみの酒場に足を踏み入れたなら、まずはそんな季節のメニューをチェックしておいて損はないだろう。
春なら筍や菜の花、冬なら白子や牡蠣だろうか。実際、私は秋になると「秋刀魚の塩焼き」に箸を伸ばしたくなる。脂がのった身にすだちを絞り、冷えた日本酒と合わせると「またこの季節が巡ってきたんだな」と実感することができる。
酒場は時の流れを映す鏡でもある。季節のものを肴に盃を傾けることは、ひとり呑みの喜びを倍にしてくれるのだ。
なじみの酒場を楽しむためのマイルール④「はじめてのメニューにチャレンジする」
「いつもの」があることは安心につながる。だがそればかりを頼んでいては、大切なひとり呑みの時間が固定化し、マンネリ化してしまうことだろう。だから私は必ず一品、冒険をするよう心がけている。
以前、なじみの酒場で「メヒカリの唐揚げ」というものをはじめて頼んだ。主に福島県などで水揚げされ、大きな目が緑色や青緑色に光ることから「目光(メヒカリ)」と呼ばれる深海魚。その当時はどんな魚なのか、どんな味かもわからなかった。だが口に運ぶと、ふっくらとした身と脂の旨味に驚かされた。それ以来、メヒカリの唐揚げを目にするたびにオーダーするほど、私の大好物となったのだから面白い。
メニューに見慣れない名前があれば、それは挑むべき新しい山。たとえ外れたとしても「酒場の失敗談」というネタに変わるのみだ。
なじみの酒場を楽しむためのマイルール⑤「おつまみは「ちょっと足りない」くらいにとどめる」

空腹のまま呑むとどうしてもあれもこれもと頼んでしまうが、一方で食べ過ぎれば、酒の旨さは霞んでしまう。だから私は「少し物足りない」くらいで止めるようにしている。
たとえば、小さな野菜系のメニューと小さな刺身盛り、そして焼鳥を数本頼んだら、もうそれ以上は追加しないという具合だろうか。小腹が空いたまま酒を楽しんだほうが、酒そのものが一層美味しく感じられる。そして帰り際に「もうちょっと食べたいな」と思えるくらいがちょうどいい。
ひとり呑みは食欲を満たすためだけの機会ではない。まして満腹になる必要など微塵もない。余白を残すことで、心地よい余韻につながるのではないかと思っている。
なじみの酒場を楽しむためのマイルール⑥「日本酒は2合まで」

私は日本酒が好きだ。できることなら毎日呑みたいし、さまざまな銘柄をたくさん呑みたいと思っている。しかし、ひとり呑みの際に奔放に日本酒を呑み続けると、とても後味の悪い思いをすることにつながりかねない。気づいたらぜんぜん関係ない電車に乗っていたとかね(実話)。無用なトラブルや翌日の自分を裏切らないためにも、私はひとり呑みの日本酒は2合までと決めている。おつまみ同様、物足りなさを残すことで、また良き思いを残したまま店を去ることで、次に訪れたいという気持ちにつなげたいから。
なじみの酒場を楽しむためのマイルール⑦「店内の音と風景を楽しむ」
酒場は、呑み食いする場所であると同時に「風景を味わう場所」でもある。焼き場から上がる煙、氷がグラスに落ちる音、常連同士の笑い声。これらすべてが酒の肴になりえるのだ。
私はときどき、スマホを完全にカバンにしまって、ただぼんやりと耳と目だけに集中することがある。すると普段は聞き流していた厨房の会話や、客がぽつりとつぶやいた一言が、不思議な味わいを持って響いてくる。酒場そのものがひとつの物語を語り始めるのだ。
なじみの酒場を楽しむためのマイルール⑧「締めたくなったら蕎麦にする」

呑みの最後はラーメンや丼ものに流れがち。私もラーメンは大好きだし、以前は締めのラーメンを食べたいがために、酒場でのおつまみは野菜系など、ごく軽めにおさえていたことすらあった。だが今では、酒場ならではのおつまみを存分に楽しみ、できるだけ締めの炭水化物を控える考え方にシフトした。それでも最後になにか食べたい気持ちが残っていた場合は、妥協案として蕎麦を食べることにしている。
酒場である程度のカロリーは接種しているのだから、酔いに任せて一食分(あるいはそれ以上)のカロリーを含むラーメンを食べてしまうなど、明らかにカロリーオーバー。自らの健康や翌朝の体調を考えても、あまり食べすぎるべきではないのだ。
と、頭ではわかっているものの、お酒を呑んだあとのラーメンの魅力に抗いきれない気持ちがあることも事実。そこをぐっとこらえて蕎麦屋の暖簾をくぐり、温かい蕎麦をたぐると、以外にも満足できることに気付いたのだ。これからは蕎麦でいいじゃないか。たまにはラーメン食べてもいいけれど、できるだけ蕎麦に頼っていきたいと考えている。
もっと豊かな酒場時間のために
ひとり呑みは、誰かと過ごす呑み会にはない自由がある。しかし、ただ自由に任せるだけでは、せっかくの贅沢な時間が埋もれてしまう。自分なりの小さなルールを設けることで、酒場でのひとときはぐっと濃密になる。なじみの店でグラスを傾けるとき、自分だけのルールについて考えてみてもいいかもしれない。それは「制限」ではなく「楽しむための工夫」。きっと次に訪れた時の酒場は、これまで以上に親しみ深いものとなるだろう。