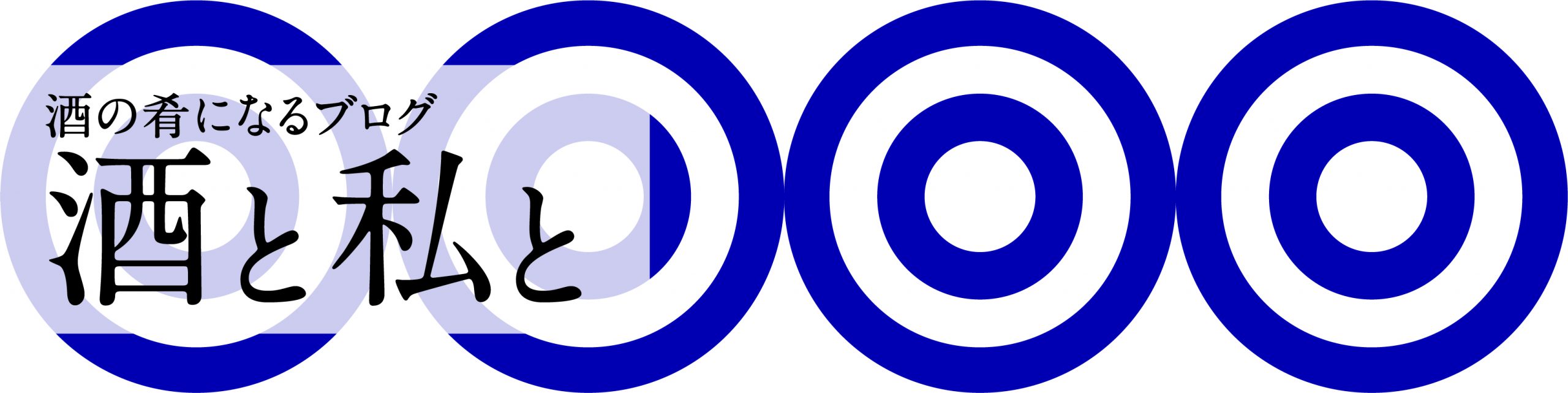毎年秋が深まる時期になると、プロ野球の優勝チームによるビールかけがテレビに映し出される。その瞬間だけは先輩も後輩も、監督もスタッフも選手も、立場も序列も超えてビールをかけ合い、喜びを爆発させる。子供のころプロ野球を熱心に観ていた私にとって、このビールかけは秋の風物詩として漠然と捉えられていた。今年もやってるな、今年の野球が終わっちゃったな、そんな他愛もない感情でその光景を眺めていたものだ。だが時が経ってプロ野球を熱心に観なくなり、お酒についてあれこれと発信する立場となった私は、このビールかけを以前とは別の視点から見るようになった。そもそもなんで優勝したらビールをかけるんだろう、海外スポーツのシャンパンファイトとは違うのかしら。寒くない?もったいなくない?チームに未成年がいたら?とっても気になったのでいろいろと調べてみることにした。
世界の泡文化:シャンパンファイトの誕生

「ビールかけ」の原型は、やはり海外の泡の文化にあったようだ。欧米では、勝利の瞬間にシャンパンを開け、その泡を勢いよく飛ばす「シャンパンシャワー」や「シャンパンファイト」という慣習が存在する。この起源として最も有名なのが、1966年のル・マン24時間レースでの出来事。スイス人レーサーのジョー・シフレが、表彰台で掲げたシャンパンの栓を開けた際、瓶が温まりすぎていたため中身が勢いよく吹き出した。それを見た観客が歓声を上げ、周囲も笑顔に包まれた。翌年、アメリカの名ドライバー、ダン・ガーニーがその出来事を再現しようと、自らの意思でシャンパンを振り、観客やチームスタッフに泡を浴びせたという。これがシャンパンファイトの始まりとされている。
以来シャンパンファイトは、F1や耐久レースなど、世界のモータースポーツ界において表彰台の定番儀式となった。やがてそれは野球、サッカー、バスケットボールなど他のスポーツにも広がり「勝利=泡を飛ばす祝祭」という図式が定着していくことになったという。
日本版シャンパンシャワーの誕生:ビールかけのはじまり

日本で初めて「ビールかけ」が行われたのは、1959年(昭和34年)のこと。南海ホークスが日本シリーズで巨人を下し、見事に優勝を果たした夜である。その祝勝会で、カールトン半田(ハワイ出身)が、アメリカで見たシャンパンファイトの風景を思い出し、手に持っていたビール瓶を仲間に向かって勢いよく振りかけた。これが「日本初のビールかけ」とされている。当時のエース・杉浦忠の頭から流れ落ちる泡、周囲の選手たちも笑いながら次々と瓶を開け、あっという間に宴は泡に包まれた。このことは当時のキリンビールの社内報でも「南海優勝!キリンで乾杯!!」という見出しとともに取り上げられるなど、この光景が新しい祝い方として話題になったという。
翌年の1960年には大洋ホエールズが同様の演出を行い、その後、セ・パ両リーグに広がっていく。昭和40年代にはプロ野球の「風物詩」としてテレビ中継されるようになり、1970年代には「優勝=ビールかけ」という公式イメージが完全に定着したと言われている。
泡の裏側に見える「違和感」
だが令和の時代になり、この恒例行事をめぐる空気は少しずつ変わりつつある。かつては「頑張った証」として微笑ましく見られた光景も、今では「古い」「不快」「もったいない」と感じる人が増えているようだ。以下のようにさまざまな角度から違和感が語られている。
飲料の浪費と倫理の問題
ビールかけには数百本、時に千本近いビールが使われることもある。そのほとんどは、飲まれることなく床に流れ落ちる。フードロスが社会問題となる現代において、この光景を「もったいない」と感じるのは当然のことだ。SNS上では「飲めばいいのに」「これがスポンサーの意向なのか」といった声も少なくない。喜びの象徴であった泡が無駄の象徴として批判の対象となる時代になったと言える。
環境と衛生の課題
ロッカールームやホテルの宴会場で行われるビールかけは、床が滑り、機材が濡れ、流れ落ちたビールが悪臭を放つ。後片付けには多大な時間とコストがかかる。また、ビールが目や口に入ることで健康被害を訴えるケースもあり、安全面からの再考を求める声も上がっている。設備の老朽化や環境意識の高まりを背景に「もうロッカールームでやる時代ではない」という意見も現実的なものになりつつある。
文化的・社会的視点からの違和感
アルコールを浴びるという行為そのものが、宗教上の禁忌に触れる場合もある。2025年には、シンガポールGPでシャンパンシャワーに参加したマレーシア人実業家がイスラム教徒として謝罪した例も報じられた。また未成年選手や飲酒を好まないメンバーにとっては(アスリートであればなおさら)、強制的に巻き込まれる構図もストレスとなる。「伝統だから」「皆やっているから」という理由で続く慣習には、現代的な倫理観とのずれが生まれつつある。
「伝統」を続ける意味を、問い直すとき
昭和から平成、令和へ。60年以上にわたって続いてきたビールかけは、日本のスポーツ史の中で確かにひとつの文化となった。しかし、それは同時に時代の鏡でもある。高度経済成長期の「勢い」や「明るさ」を象徴した儀式が、成熟社会では「浪費」や「ハラスメント」として映る。文化とは、そうやって見え方を変えていくものだ。
伝統を守ることは大切。だが守るためには「変える勇気」も必要である。もしその儀式が誰かを不快にし、社会的責任を問われる時代になったなら、私たちはその形を更新していくべきではないだろうか。
新しい祝杯のかたちへ

近年では、炭酸水やノンアルコールビールなど、ビール以外の飲料を使うチームも出てきているし、サッカーの代表チームは試合直後にピッチ上で水をかけあいながら喜びを爆発させている。こんな動きから予想できるように、今後は年齢や宗教上の理由を問わず、全員で楽しむことができる新しい祝祭の形が定着していくのではないだろうか。泡はなくても、喜びは薄れない。大切なのは「かける」ことではなく「分かち合う」こと。試合直後に喜びを爆発させたあと、その余韻を静かに味わいながらゆっくりと一杯を呑み飲み干す。そんな祝杯の風景も悪くないだろう。
ビールかけは、選手たちの汗と涙が泡に変わる瞬間である。その美しさを否定することはもちろんできないが、その泡の向こうには、資源、倫理、そして時代の価値観がある。「かける」か「飲む」か。その選択は、これからのスポーツ文化の成熟を映す鏡になるだろう。