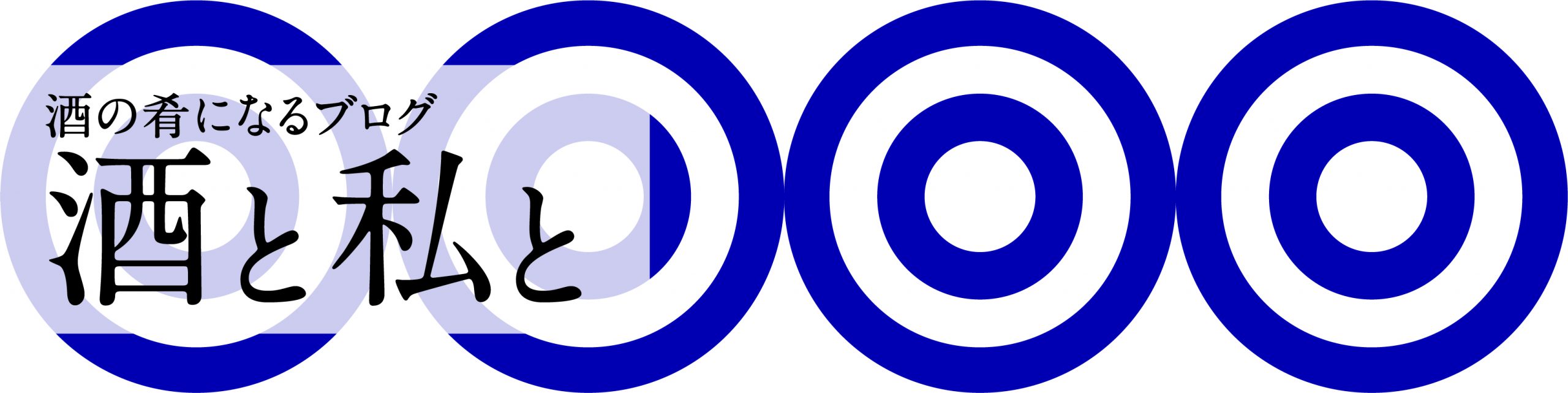焼き鳥を頼んだのに、出てきたのは豚のカシラやシロだった。「やきとり」と書かれた赤提灯をくぐると、そこには鶏ではなく豚の串がずらりと並んでいる。特に関東圏では、そんな経験をしたことがある人は多いのではないだろうか。初めての人は少し戸惑うはずだし、かつての私ももれなく戸惑ったものだ。この現象は一体何なのだろうか。調べてみると、これにはどうやら歴史的な背景や地域性が関係していることがわかる。今回の記事では「なんで豚肉なのに焼き鳥っていうの?おかしくない?」について、その理由と背景を紐解いていこうと思う。
焼き鳥の原型は「鶏」ではなく「串焼き」

「焼き鳥」という言葉が登場したのは江戸時代後期から明治期にかけてのことと言われている。当時は鶏肉よりもスズメやウズラ、鳩、さらには魚や野菜まで、さまざまな素材を竹串に刺して炭火で焼く料理が屋台で親しまれていた。つまり「焼き鳥」とは、もともと「鳥を焼く料理」ではなく「串に刺して焼く」という調理形式そのものを指していたということになる。
江戸の庶民にとって、鳥はまだまだ高級品。当時の屋台では鳥に限らず、手に入りやすい素材を工夫して焼くことが一般的だったのだ。鶏肉を日常的に食べられるようになったのは、もっとずっと後の時代の話である。
鶏が消え、豚が台頭した戦後の食糧難の時代

「豚肉なのに焼き鳥」という不思議な現象が定着した大きなきっかけは、戦後の食糧難にある。敗戦直後の日本では鶏の供給が追いつかず、代わりに各地で養豚が盛んになった。特に群馬・埼玉・東京といった関東圏では、豚肉が身近なタンパク源として広く出回るようになったと言われている。
そんな事情もあり、もともと焼き鳥屋を営んでいた屋台などでは、鶏肉の代わりに豚肉を使用することとなる。串打ち、炭火焼き、タレや塩の味付けなどの調理スタイルはそのままに、材料だけが鶏から豚に置き換わったのだ。それにも関わらず、屋台の看板は「やきとり」のまま。これが結果として「焼き鳥=豚串」という文化が一部地域に根付くきっかけになったのである。
今日では「焼きとん(焼き豚の略)」という言葉があるが、これは昭和中期以降に定着した比較的新しい呼び名。「うちは豚専門」ということで、鶏をメインとしている店との差別化をはかるためとも言われている。
地域で異なる「焼き鳥」の意味

面白いのは、地域によって「焼き鳥」という言葉の持つ意味が少しずつ違うということだ。関東の一部、埼玉や群馬、東京の下町エリアなどでは、これまで述べてきたように「焼き鳥=豚の串焼き」という意味を持つことが多い(そのまま鶏を出す店も多いけれど)。それに対して関西や九州では「焼き鳥=鶏肉の串焼き」とそのままの意味で使用されている。また北海道や東北の一部では「焼き鳥=鶏、豚、牛、なんでもアリ」ということのようだ(事実と相違のある場合はご指摘ください)。
つまり「焼き鳥」という言葉そのものが、地域の食文化の鏡になっていると言っても過言ではない。「焼き鳥」と聞いて想像する肉が違う。それだけでどの地方の出身かが分かるなんて興味深い話ではないだろうか。
現代の“焼き鳥”は「形」の文化

今や「焼き鳥」は単なる料理名ではなく、日本の大衆食文化の象徴になっている。炭火を前に、煙にまみれながら一本ずつ串を焼く。焼き台の向こうにはそんな職人の手さばきがあり、カウンターのこちらにはビールを傾ける客がいる。その光景こそが「焼き鳥」の本質であり、それが鶏であろうと豚であろうと「焼き鳥」というフォーマットの中ですべてが完結する。私たちの「一杯やりたい」という抗えきれない欲求、それを満たしてくれる場所のことを、いつの時代も「焼き鳥屋」と呼んできた。この素晴らしい文化はこれからも、絶えず続いていくことだろう。