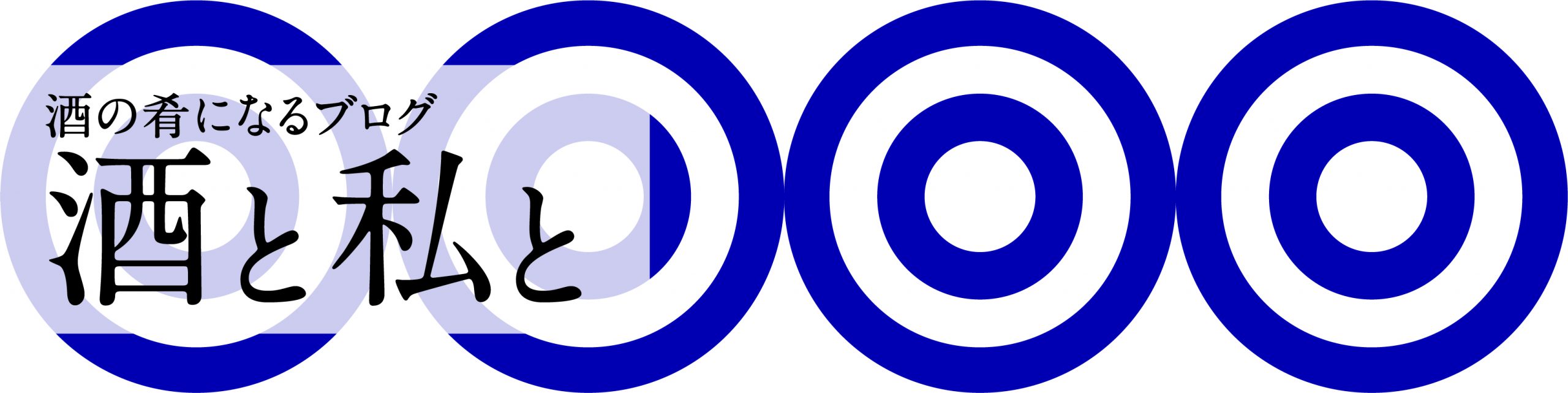私は基本的に、お酒が呑めれば後のことはだいたい何でもいい、という趣向で酒を呑んできた。どこで呑もうが、何をつまみにしようが、コップでも茶碗でもお酒がこぼれなければ何でもいい、と思っていた。
ところが近年、私のそのいい加減極まりない趣向に大きな変化が訪れた。日本酒にしっかりと向き合いたいと思うようになったのだ。日本酒の造りや成り立ち、なによりその味わいの奥深さに、これはこのあとの人生を使って探求するべき価値が大いにあると気付かされたのだ。同時に、酒蔵や杜氏、蔵人たちが丹念に磨き上げたお酒を、これまでのように適当な器で呑むのはちょっと失礼にあたるのではないかとも思うようになった。そして適当な器では、日本酒の香りや味わいや、その魅力をしっかりと楽しむことができないのではないかと。そんな思いがふつふつと湧き出てきた直後、私が手にしていたのが「利き猪口(ききちょこ)」だった。
湯呑み茶碗にも似たこの利き猪口を手に入れたことで、私の日本酒ライフは大きな広がりを見せ、さらに奥行きも深くなったと感じている。こんなものを使うだけでいったい何が変わるというのか?その驚くべき効果について語っていこうと思う。
日本酒の魅力を最大限に引き出す「利き猪口」

日本酒を愛する者なら一度は目にしたことがあるだろう利き猪口という器。白地に藍色の二重丸が描かれた、極めてシンプルでありながら美しさが際立つ陶器だ。特に私が手に入れた1合(約180ml)サイズは、酒蔵や日本酒イベントでも使われており、日本酒の魅力を最大限に引き出すための工夫が随所に込められている。またこの大きさは家で日本酒を楽しむには丁度よく、1杯で1合、今日は2合でやめておこうか、などと自分で酒量を把握することも容易となることが密かに気に入っている点でもある。
利き猪口の起源は江戸時代にさかのぼるとされる。もともと「猪口(ちょこ)」は酒を飲むための小さな器の総称であったが、酒蔵や杜氏が日本酒の品質を評価・確認するために使う「利き猪口」が誕生したことで、独自の意味を持つ器となった。かつては酒蔵ごとにさまざまな形状や大きさの猪口が使用されていたが、明治以降、酒質の統一的な検査や品評会の場において一定の規格が設けられることとなり、現在の姿になったということだ。
お酒の色合いを鮮やかに映す白地と「蛇の目」のコントラスト

利き猪口の内側(底)には、白地に藍色の二重丸、いわゆる「蛇の目」模様が描かれている。この模様は単なる装飾ではなく(装飾としても非常に優れていると感じるが)、日本酒の色や透明度、濁り具合を判別しやすくする実用的な役割を果たしている。酒を注いだ際に、白と藍のコントラストが明確に現れ、日本酒の色合いがよりはっきりと見える。
白磁の表面は光をよく反射し、微妙な色の違いも視認しやすいため、酒質の評価に最適とされる。同じ純米酒でも熟成が進んだものはやや黄色みを帯び、搾りたては無色透明に近い場合が多いが、利き猪口を用いることでその違いが一目瞭然に。お酒をまずは目で楽しむことができるというわけだ。
温度によって刻々と変化する香りと味わいを楽しむ

私が利き猪口を使いはじめてもっとも感銘を受けたのが、温度によって日本酒の味や香りが如実に変化していくことだった。
まずは冷蔵庫から出したばかりのお酒を注ぎ、そのまま香りを嗅ぎ、ひと口含む。まだ冷たさを残した酒は、淡麗で凛とした印象を与えることが多い。しかし、利き猪口をしばらく手で包んでいると自分の体温が器に伝わり、お酒の温度が少しずつ上昇していく。
やがて「人肌燗(約35℃)」と呼ばれる温度帯が近くなると、お酒の表情ががらりと変わる。香りがふわりと立ち上がり、味わいにはまろやかさが加わる。これまで控えめだった甘味が前面に出てくることもあれば、酸味やコクがより明確に感じられることもある。
さらに利き猪口ごと小鍋に入れて湯煎することで温度を上げ「ぬる燗(約40℃)」の域にいたると、お酒は一段と豊かな香味を見せる。特に純米酒や生酛系の酒では、熟成感や米の旨味が際立ち、酒そのものの個性がくっきりと浮かび上がってくる。味の「ふくらみ」とも言うべき、奥行きある輪郭が感じ取れるのだ。
酒器によって味が変わる、というと大げさに聞こえるかもしれない。だが実際に利き猪口で飲み比べてみると、それが事実であることに驚かされる。常温での酒、手で温めた酒、ぬる燗の酒。同じ銘柄であっても、まるで別の酒であるかのような印象を受けることさえある。これは、単に温度が変わったという物理的な要因だけではない。猪口の形状や厚み、口当たりの変化、そして飲み手の「意識」の持ちようによって、味わいはより繊細に感じられるようになるのだ。
温度によって刻々と変化する香味の移ろいを、手のひらの中で静かに味わう。これこそが、利き猪口で楽しむ日本酒の醍醐味なのではないかと感じている。
1合の小さな器の中に、大きな宇宙が広がっている

利き猪口は実際、ただの小さな器にすぎない。だが、その中には日本酒の世界をより深く、豊かに味わうための知恵が詰まっている。1合というちょうど良いサイズ、温度による変化を受け止める厚み、そして酒の色や香りを引き立てる蛇の目模様。もはや他の酒器と同列に語るものではないように思う。
日々の晩酌にこの器を取り入れてみると、酒との向き合い方が少しだけ変わる。ひと口飲むごとに、温度の変化とともに酒が語りかけてくる。そんな時間が持てることは、きっと酒好きにとって何よりの贅沢だろう。
「1合の器に宇宙がある」。そんな言葉さえ、決して大げさではないと思えてくるのだ。